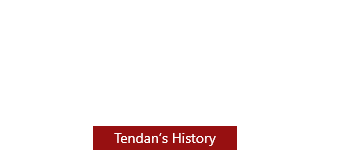
日本における焼肉創世記よりお店を構え、
今では京都で多くの方に知って頂ける
焼肉レストランとなった天壇。
1965年京都祇園の地に開業して以来、
焼肉の名門天壇はどのような道を歩んできたのか。
その軌跡をご紹介します。
since1965
「焼肉という食文化の発展」
その情熱が私たち天壇の原点です。
天壇が創業した1965 年は、
前年10 月に東京オリンピックが開催され新幹線が開通するなど、
日本が急速に経済発展する一方で、
人々はまだゆったりとした時間のなかを生活している、
そんな二者が共存していた時代でした。
今からは想像がつきませんが、「焼肉」というのはまだ
一部の人しか食べていない料理ジャンルでした。
「日本はこれから経済的に豊かな国となり、
いろいろな食が広がるだろう。
その時美味しい焼肉は必ず多くの人に支持されるはずだ。」
そう考えた創業者の新井東鉉は
「焼肉」という食文化を京都から広めることを胸に誓い、今の祇園本店の地で「天壇」を開業しました。
1965年 天壇創業当時の四条大橋
(撮影:風間克美)

お出汁のような「つけたれ」で
食べる焼肉の誕生
創業当時、焼肉とはどんな料理かを伝えるために、
一般的に「大陸料理」や「バーベキュー」という表現を使っていました。
天壇でも「焼肉」という言葉を使いはじめたのは創業よりあとのことです。
そんな時代に、どうすれば「焼肉」を受け入れてもらえるか?
当時の焼肉は「塩焼き」という概念はなく、全てが濃い味の「タレ焼き」でした。
そこで天壇が採用したのが、「お出汁のようなつけたれ」で召し上がっていただく現在の「京都焼肉」と呼ばれる食べ方でした。
味付けをしたお肉をこの「つけたれ」で自分好みの味に変化させ、食べ頃の温度で召し上がっていただく食べ方は、
少しづつ京都の方に好まれ、愛されるようになりました。
京都独自の焼肉文化を
育んできた天壇
京都では、天壇のつけたれのようなお出汁のようなつけたれを出す焼肉店が多く、
余分な脂を洗い落とすようにして食べる様から、一般的には「洗いダレ」と呼ばれることが多いです。
天壇の創業当時は大阪や京都においてこの「洗いダレ」を提供している店舗は多くありましたが、
時代とともに少なくなり、現在はほぼ京都のみで見受けられます。
つまりこの食べ方は京都独自の焼肉文化と言えるでしょう。
地元京都では「初めて焼肉を食べたのは天壇だった」と仰る方も多く、京都在住の作家、柏井壽さまの著書では、天壇を「京都焼肉の原点」とご紹介いただいております。
※著書『「京都の定番」(柏井壽著 幻冬舎新書より)』

天壇のこれから
京都の地に深く根付き、育んできた天壇の味は守りつつ、
時代のニーズを見極め、常に新たな挑戦を続けていきます。
そして、これからも「焼肉」という食文化と向き合い、創造していきます。

天壇祇園本店

西院店

桂五条店

The Dining
山科店

北山店

草津店

銀座店

大門店

赤坂店

竹田店























